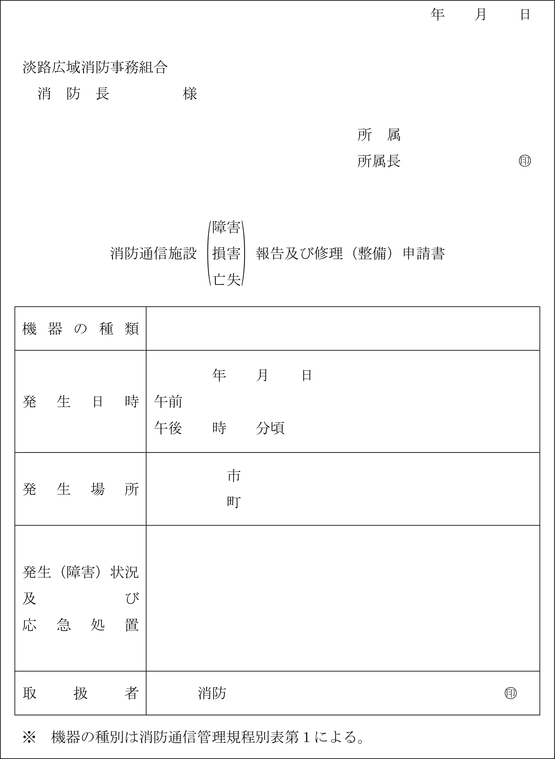○淡路広域消防事務組合消防通信管理規程
平成9年3月28日訓令第79号
淡路広域消防事務組合消防通信管理規程
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 運用
第1節 有線通信(第14条~第18条)
第2節 無線通信(第19条~第30条)
第3節 記録(第31条)
第3章 点検及び整備(第32条~第35条)
第4章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、淡路広域消防事務組合に属する消防通信施設の適正な管理保全並びに消防通信の能率的な運用を図るため、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信施設とは、
別表第1に掲げる施設をいう。
(2) 情報システム装置とは、
別表第2に掲げる施設をいう。
(3) 通信指令室とは、通信業務を行うために消防本部(以下「本部」という。)に設けられた人的、物的施設の一体をいう。
(4) 通信業務従事者(以下「従事者」という。)とは、
別表第3に掲げる通信施設の通信操作に従事する者をいう。
(5) 通信機器取扱者(以下「取扱者」という。)とは、
別表第3に掲げる通信機器を取り扱い、又は通信を行う者をいう。
(6) 無線従事者とは、
別表第3に掲げる無線通信機器を取り扱い、又は通信を行う者をいう。
(7) 指令とは、水火災、救急、救助及びその他災害(以下「災害等」という。)を覚知した場合において、本部から消防署、分署及び出張所(以下「署所」という。)に対して予告、出動、出場(以下「出動」という。)の命令を発する通信をいう。
(管理責任)
第3条 消防長は、消防通信施設及び情報システム装置(以下「通信施設等」という。)の運営業務を管理するものとする。
(管理権の委任)
第4条 消防長は管理権の一部を委任するため、通信業務管理者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 前項に規定する管理責任者は、消防課長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事務を掌握するものとする。
(1) 電波法(昭和25年法律第131号)、公衆電気通信法(昭和28年法律第97号)等関係法令の規制に関する事項の遵守に関すること。
(2) 通話及び通信障害に関すること。
(3) 通信施設等の保全計画の策定に関すること。
(4) 通信障害の未然防止と改善研究に関すること。
(5) 従事者に対する運用指導及び研修に関すること。
(6) 関係書類の管理に関すること。
(7) その他通信業務に関すること。
2 署所の通信施設等についての運用管理は、署長、分署長及び出張所長(以下「所属長」という。)が行う。
(通信指令室の業務)
第6条 通信指令室は、災害等の状態を迅速に把握し、その災害活動及び救急業務(以下「災害活動等」という。)に関する必要な指令、消防隊の統制的運用、通信の管理統制及び情報の収集等を実施し、災害活動等の効果をあげるものとする。
(通報の受理)
第7条 通信指令室が通報を受理するときは、災害の発生場所、対象名、災害の状態、その他必要な事項を確認するよう努めなければならない。
(消防隊の掌握)
第8条 通信指令室は、消防隊の統制的運用を行うため必要な消防隊の編成及び災害活動等の実施に際し、出動可能な消防隊の状況等を常に掌握しておかなければならない。
(従事者等の責務)
第9条 従事者、取扱者及び無線従事者(以下「従事者等」という。)は、関係法令及びこの規程に定める事項を遵守し、通信施設等の機能の精通に努めるとともに、常に冷静な判断と通信施設等の正確な操作により能率的な通信機能の活用を図るものとする。
(従事者等の留意事項)
第10条 従事者等は、通信施設等の操作について、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 迅速、正確を旨とすること。
(2) 呼出信号のあったときは、速やかにこれに応ずること。
(3) 通信内容及び通話内容は簡潔、明瞭に行うこと。
(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又は独断で処理しないこと。
(5) 必要な通信事項は記録と保存をすること。
(6) みだりに所定の場所を離れないこと。
(7) 通信施設等の保全に努めること。
2 従事者等は、通信により知り得た機密の保持を厳守しなければならない。
(従事者等の精通事項)
第11条 従事者等は、次の各号に掲げる事項について精通しなければならない。
(1) 火災出動区分、救急出場区分、管内全般の町名、地勢その他消防事象全般について常に研究し、熟知すること。
(2) 通信施設等の機能を熟知し、その操作に精通すること。
(通信種別)
第12条 消防通信は、有線通信及び無線通信とし、通信内容により緊急性を有する指令及び通報(以下「緊急通信」という。)とその他の通信(以下「普通通信」という。)に区分する。
2 緊急通信は、災害等の発生に伴って運用する通信をいう。
3 普通通信は、前項以外の通信をいう。
(通信優先順位)
第13条 緊急通信は、普通通信に優先する。
2 緊急通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害発生の受信に関すること。
(2) 出動等指令に関すること。
(3) 増強部隊の出動要請に関すること。
(4) 指揮命令に関すること。
(5) 災害現場即報に関すること。
(6) 前各号以外で緊急事項に関すること。
3 前項に掲げる緊急通信の順位は、同項各号の順位によるものとする。
第2章 運用
第1節 有線通信
(不確実通報による措置)
第14条 従事者等は、119番回線に不確実な通報があった場合又は通報の聴取後であっても回線を一時保留状態に置き、災害場所及び災害状況について再確認に努めなければならない。
(勤務者の通報)
第15条 署所の受付その他の勤務者が災害等を覚知したときは、直ちに本部へ通報しなければならない。
(出動指令及び関係機関)
第16条 従事者等は、災害等を覚知し、又は特別命令を受けたときは、必要事項を聴取確認後、直ちに自動選別指令、一斉指令等により署所に出動を指令しなければならない。また、必要事項を関係機関に通報しなければならない。
(指令電話による一般業務通信)
第17条 従事者等は、本部、署所に非常召集、気象情報の発令等同一内容の通知を行う必要がある場合は、一斉指令等により通知することができる。
2 署所の受付勤務者は、前条の指令及び前項の通知を受信したときは、内容を確認後、署所端末装置の操作を行わなければならない。
(指令信号)
第18条 指令信号は、別に定める。
第2節 無線通信
(無線施設)
第19条 無線施設は、基地局及び陸上移動局(以下「無線局等」という。)とする。
3 陸上移動局は、消防長の指定する場所に配置する。
(無線局等の呼出名称等)
第20条 無線局等の呼出名称、種類、チャンネル及び周波数は、別に定める。
(無線局等の所管)
第21条 所属長は、消防長の命を受け、第19条の規定に基づき配置された無線局等を管理し、担当区域における無線通信の責に任ずるものとする。
(携帯無線機の運用)
第22条 災害時に出動する指揮者は、携帯無線機の携行に努め、現場における効果的運用を図らなければならない。
(無線局等の開局及び閉局の制限)
第23条 基地局は、常に開局しておかなければならない。
2 陸上移動局は、通信を行う必要がある場合に開局するものとする。ただし、災害等の出動にあっては開局後、帰署するまでの間は原則として閉局してはならない。
(法定資格)
第24条 無線従事者は、法令に定める資格を有する者でなければならない。また、その資格に応じた範囲外の無線通信及び通信機器の取扱を行ってはならない。
(無線設備の操作)
第25条 無線局等の無線設備の操作は、選任された無線従事者が行うものとする。
(無線通信の統制)
第26条 管理責任者は、円滑な無線運用を図るため各陸上移動局の通信内容の緊急性を考慮し、通信順位の決定及び通信停止等の措置を行うことができる。
(無線通信の内容制限)
第27条 無線通信の内容は、消防業務遂行に必要な事項で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 消防業務の運営管理並びに行政管理に関する事項
(2) 法令等に定める非常通信と認められる事項
(3) その他消防業務遂行について、特に消防長が認め他の法令等に抵触しない範囲の事項
(無線通信の混信防止)
第28条 無線従事者は、他の無線局等に対し、その運用を阻害するような混信電波の発射その他の妨害をしてはならない。
(陸上移動局の出動中の所管及び無線連絡)
第29条 災害等に出動した陸上移動局の通信は、本節の規定に基づき消防長の指揮に従い必要な消防通信を行うものとする。
2 陸上移動局が災害活動のため出動し、帰署するまでの間における基地局への無線連絡の内容は、次の各号に定めるところによる。ただし、車両運用端末装置(AVM)を最大利用するものとする。
(1) 開局出発
(2) 現場到着及び災害の状況
(3) 災害活動等の状況
(4) 引き揚げ
(5) 帰署(所)閉局
(6) その他必要事項
(その他)
第30条 通話上の留意事項
(1) 通話は簡潔、短時間に行う。
(2) 長時間の通話は、有線電話連絡に切り替えること。
第3節 記録
(無線業務日誌)
第31条 基地局には、電波法に基づく無線業務日誌を備え、必要事項を記録しなければならない。
第3章 点検及び整備
(点検の種類)
第32条 通信施設の点検は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検 所属長は、
別表第5により毎日1回以上通信施設の点検を行うものとする。
(2) 定期点検 所属長は、毎月1回以上通信施設等の点検を行わなければならない。ただし、当該点検を保守点検業者に委託することができる。
(3) 特別点検 サイレン吹鳴装置については、必要に応じ作動特別点検を行うものとする。
(定期検査にかかる自主検査)
第33条 管理責任者は、電波法第73条に定める定期検査のため毎年1回法定点検事業者に委託し、自主検査を行わなければならない。
(試験通信)
第34条 管理責任者は、指令回線及び無線電話の機能試験のため毎日定時に試験通信を行い、その結果を記録しなければならない。
2 指令回線の試験通信を臨時に行う場合は、事前に相手方に連絡するものとする。
3 従事者等が臨時に無線電話の試験通信を行う場合は、事前に相手局にその旨を連絡するものとする。
(事故発生時の措置)
第35条 従事者等は、通信施設等に障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、
別表第6により応急措置を行うとともに所属長を経由して管理責任者に報告しなければならない。
2 従事者等は、通信施設等の損傷又は亡失事故等が発生した場合、直ちに事故内容及び発生原因を記録し、所属長を経由して
別記様式により管理責任者に報告及び申請しなければならない。
3 管理責任者は、前2項に規定する報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるものとする。この場合において、消防通信上重大な支障があるものについては、直ちにその概要を消防長に報告しなければならない。
第4章 補則
(補則)
第36条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(淡路広域消防事務組合無線局運用管理規程の廃止)
2 淡路広域消防事務組合無線局運用管理規程(平成元年淡路広域消防事務組合訓令第58号)は廃止する。
附 則(平成16年3月29日訓令第127号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日訓令第194号)
この規程は、平成27年3月10日から施行する。
附 則(平成31年4月18日訓令第219号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年2月19日訓令第225号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1号関係)
消防通信施設分類表 |
種別 | 摘要 |
情報通信施設 | 消防指令センター各装置、庁内電話装置 |
衛星通信ネットワーク、災害対応総合情報ネットワーク、広域災害救急医療情報システム |
無線通信施設 | 基地局 | 陸上移動局と通話を行うため、消防機関あるいはその他の施設内に設置された移動しない無線設備 |
陸上移動局 | 自動車等移動体に設置された無線局設備及び携帯用無線局並びに付属機器 |
別表第2(第2条第2号関係)
情報システム分類表 |
種別 | 摘要 |
自動出動指定装置 | 指令台等に設置し、災害通報受付から災害区分、種別を決定するとともに、出場部隊の編成、出場指令処理、消防隊の活動状況等の処理を行う装置 |
地図検索装置 | 指令台等に設置し、自動出動指定装置と連動し、災害地点周辺の地図をディスプレイに表示できる装置 |
署所端末装置 | 署所等に設置し、指令電話の発着信、署所拡声装置の制御及び車両運用状況の入力設定及びプリンタ装置により出動指令書の出力が行える装置 |
長時間録音装置 | 回線毎に録音・再生を行う装置 |
非常用指令設備 | 指令台の障害時に受付指令業務を補完する装置 |
表示装置 | 指令状況、車両運用状況等の把握及び指令台、指揮台、地図検索装置の画面モニター、情報収集用の画像等を多目的表示装置に切替表示をする装置 |
災害状況等自動案内装置 | 火災等の情報を音声合成装置を利用し案内する装置 |
順次指令装置 | 音声合成装置により作成された合成音声等により災害種別に応じた指令先に連絡する装置 |
音声合成装置 | 予告指令、出場指令、連絡放送時等において、自動的に音声合成ができる装置 |
出動車両運用管理装置 | 車両の動態情報、位置情報を管理する装置 |
無停電電源装置 | 非常用電源装置 |
別表第3(第2条第4号、第5号、第6号関係)
通信業務従事者、通信機器取扱者及び無線従事者の従事区分 |
通信施設及び機器類 | 従事及び取扱区分 |
通信指令施設・他 | 従事者(指令係員) |
署所端末装置・他 | 取扱者(署所勤務者) |
庁内電話機器・他 | 従事者及び取扱者(指令係員及び署所勤務者) |
基地局用無線機器・他 | 無線従事者 |
別表第4(第19条関係)
基地局の配置一覧表 |
基地局名 | 設置場所 | 所在地 |
あわしょう ほんぶ | 消防本部 | 洲本市塩屋一丁目2番32号 |
あわしょう ゆら | 由良出張所 | 洲本市由良町由良2353番 |
あわしょう つな | 津名一宮分署 | 淡路市中田3724番地2 |
あわしょう ごしき | 五色出張所 | 洲本市五色町都志304番地4 |
あわしょう いわや | 岩屋分署 | 淡路市岩屋2942番地16 |
あわしょう ほくだん | 北淡出張所 | 淡路市育波478番地2 |
あわしょう なんだん | 南淡分署 | 南あわじ市賀集八幡29番地1 |
あわしょう ふくら | 大鳴門橋記念館 | 南あわじ市福良丙936番地3 |
別表第5(第32条第1号関係)
日常点検項目 |
種別 | 番号 | 項目 |
通信機器 | 1 | 通信機能 |
2 | 機器外面の汚損状態 |
3 | 機器及びその収容部の水分付着状態 |
4 | 制御器、送受話機、スイッチ、つまみ及びランプの動作取付状況 |
5 | アンテナのあるものはアンテナの取付及び汚損状態 |
6 | 電源用切替スイッチの切替及び取付状態 |
7 | 電源用蓄電池の充電状態 |
8 | コードのねじれ及び被覆の破損状態 |
9 | ハンドセットのコードの状態 |
10 | 増幅器の動作状態 |
11 | ねじ類や接栓類のゆるみの状態 |
12 | テスト時の送受信状態 |
13 | 業務終了時のスイッチ及びつまみ類の状態 |
別表第6(第35条関係)
無線機障害措置要領 |
障害模様 | 原因 | 点検箇所 | 措置 |
送信及び受信ができない | 1 ヒューズ切れ又はバッテリーの劣化 | ヒューズ又はバッテリー | ヒューズ又はバッテリーを交換する。 |
充電不足の場合は十分充電する。 |
2 電源スイッチ不良 | 電源スイッチ | スイッチを交換する。 |
3 アンテナ等の接栓のゆるみ及びアンテナの折損 | アンテナ系 | アンテナ等の接栓を締めつける。 |
アンテナの折損は交換する。 |
4 スピーカマイクの不良 | スピーカマイク | スピーカマイクを交換する。 |
5 水ぬれ | 無線機本体及びスピーカマイク | 十分乾燥する。 |
送信ができない | 1 ハンドセット又はスピーカマイクの不良 | ハンドセット又はスピーカマイク | ハンドセットのプレストークスイッチの接点を清掃する。 |
カールコードの断線は交換する。 |
スピーカマイクを交換する。 |
2 通信チャンネルが他局使用中になっている | 送信部 | 他局使用中が無くなるまで待ってからプレスボタンを押す。 |
3 アンテナ等のゆるみ及びアンテナの折損 | アンテナ系 | アンテナ等の接栓を締めつける。 |
アンテナの折損は交換する。 |
電波は出るが音声がのらない | 1 ハンドセット又はスピーカマイクの不良 | 送話器 | 送話器を交換する。 |
スピーカマイク | スピーカマイクを交換する。 |
2 アンテナ等の接栓のゆるみ及びアンテナの折損 | アンテナ系 | アンテナ等の接栓を締めつける。 |
アンテナの折損は交換する。 |
送信出力が低下した | 1 アンテナの折損 | アンテナ系 | アンテナの折損は交換する。 |
2 電源電圧の低下 | 電源部及びバッテリー | バッテリーを交換する。 |
充電不足の場合は十分充電する。 |
受信ができない | 1 スピーカ又はスピーカマイクの不良 | スピーカ又はスピーカマイク | スピーカを交換する。 |
スピーカラインのショート又は断線は修繕する。 |
スピーカマイクを交換する。 |
2 ハンドセットの不良 | 受話部 | 受話器を交換する。 |
カールコードの断線は交換する。 |
3 アンテナ等の接栓のゆるみ及びアンテナの折損 | アンテナ系 | アンテナ等の接栓を締めつける。 |
アンテナの折損は交換する。 |
受信感度が低下した | 1 受信高周波部の調整ずれ | 受信高周波部 | 受信高周波部の再調整をする。 |
2 アンテナの折損等 | アンテナ系 | アンテナの折損は交換する。 |
電源が入らない | 1 ヒューズ切れ | ヒューズ | ヒューズを交換する。 |
2 電源スイッチ不良 | 電源スイッチ | スイッチを交換する。 |
3 電源ケーブルの断線 | 電源ケーブル | 電源ケーブルを交換する。 |
4 バッテリーの不良 | バッテリー | バッテリーを交換する。 充電不足の場合は充分充電する。 |
 別記様式
別記様式(第35条関係)