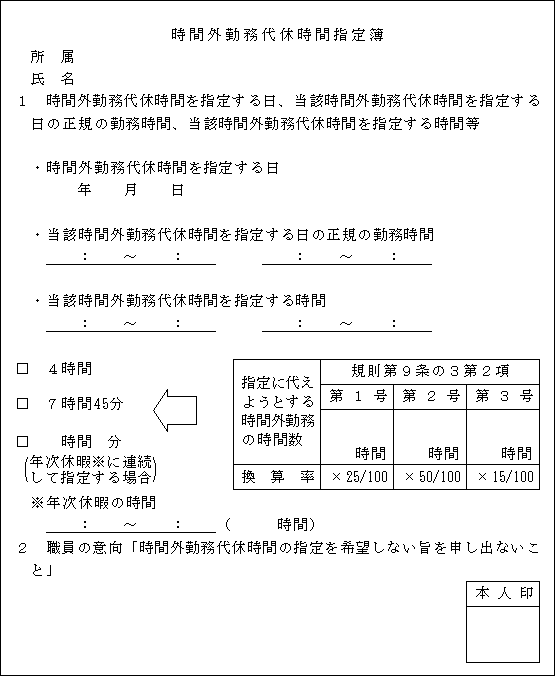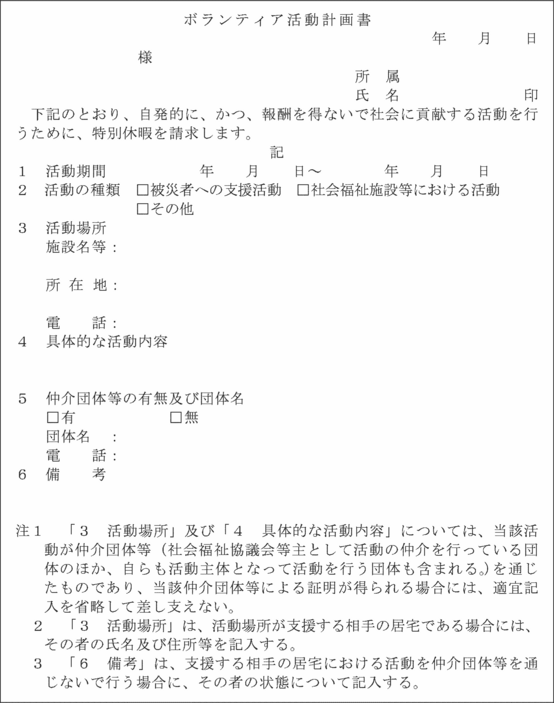○淡路広域消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する実施規程
平成9年9月16日訓令第84号
淡路広域消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する実施規程
(目的)
第1条 この規程は、淡路広域消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第133号。以下「条例」という。)及び淡路広域消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年規則第94号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項及び第4条第1項の規定に基づく勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。ただし、隔日勤務を行う職員(以下「隔日勤務者」という。)に対して行う条例第4条第1項の規定に基づく勤務時間の割振りは、勤務体制を2交代制とし、午前9時から翌日午前9時までの間に、2日分の勤務時間として15時間30分を割振るものとする。
2 前項本文の規定に関わらず、毎日勤務者にあって、その勤務形態が隔日勤務者の勤務形態と一体を成すものと消防長が特に認める者についての条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間の割振りは、午前9時から午後5時45分までの間に行うものとする。
3 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、隔日勤務者については、本文の休憩時間に加え午後5時45分から午後6時30分まで、午後9時30分から午後9時45分まで、翌日午前0時から午前6時まで及び午前7時から午前7時30分までの各時間とする。
4 条例第7条に規定する休息時間は、午後5時30分から午後5時45分まで及び午後9時45分から午後10時までとする。
5 条例第6条第2項に規定する職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があり、休憩時間を一斉に与えないことができる業務とは、消防通信業務とする。
6 規則第2条第2項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合は、割振り単位期間を8週間とし、期間内に16日の週休日を設けるものとする。
7 規則第5条の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振り内容の明示は、週休指定表により行うものとする。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条に規定する特に勤務することを命ずる必要がある場合に該当する業務の範囲は、事前に計画され、組合等が実施する大会、行事、試験、研修及び講習会等とする。
2 一の週休日について、規則第3条第2項に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。
3 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
4 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
5 4時間の勤務時間の割振り変更は、午前又は午後の半日単位として行うことができるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条の2 規則第9条の3第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。
2 条例第8条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給与の支給定日までに行うものとする。
3 時間外勤務代休時間指定簿の様式は別紙様式第1のとおりとする。
4 時間外勤務代休時間指定簿は、一の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について同一の時間外勤務代休時間指定簿によることができる。
(代休日の指定)
第4条 規則第21条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 勤務を命ぜられた休日の前日までに代休日を指定されている職員が、当該休日に年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けた場合は、条例第12条第2項の「勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合」として取り扱うものとする。
(年次休暇)
第5条 規則第23条第5項の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、条例第14条第1項第3号に規定する国家公務員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次休暇の日数は、当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第23条第1項第3号又は同条第4項第2号の規定を適用した場合に得られる日数とする。
2 条例第14条第2項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇)
第6条 条例第15条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
2 1時間を単位として使用した病気休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(特別休暇)
第7条 規則第28条の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(2) 第4号の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(3) 第4号アの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(4) 第4号イの「管理者が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウ及びキに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具制作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設及び児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに自動発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
ケ アからケまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって管理者が定めるもの
(5) 第4号ウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
(6) 第6号の「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、出産予定日の前日から起算するものとする。
(7) 第7号及び第9号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
(8) 第18号の「原則として連続する5日」の取扱いについては、暦日によるものとし、必要があると認められる場合には1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
(9) 第20号の「等」には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第2項及び第19条第1項の措置又はこれに準ずる措置を受けた場合を含む。
(介護休暇)
第8条 条例第17条第1項の「指定期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。
2 規則第29条第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊り込む場合等を含む。
3 規則第29条第1項第2号の「管理者が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
(5) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
4 介護休暇の請求等は、次によるものとする。
(1) 介護休暇の請求は、承認を受けようとする期間の始まる日から起算して1週間前の日までに行うものとし、要介護者の一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求するものとする。
(2) 任命権者は、介護休暇の請求期間のうちに公務の運営に著しく支障がある日又は時間を除き、介護休暇を承認するものとする。この場合において、介護休暇の請求期間の全部又は一部について承認しなかった場合には、当該承認しなかった日又は時間を職員に通知するものとする。
(3) 任命権者は、承認を行った後、特定の日又は時間に公務の運営が著しく支障があるときは、当該特定の日又は時間について承認を撤回することができる。この場合において、任命権者は、当該承認を撤回した日又は時間を職員に通知するものとする。
(4) 介護休暇の承認を受けて職員が要介護者を介護する必要がなくなった場合又は承認を受けた期間の一部について要介護者を介護する必要がなくなった場合には、介護休暇承認の変更を申請しなくてはならない。
(5) 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
(休暇の承認等)
2 任命権者は、7日以上継続する病気休暇を承認するに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。
3 任命権者は、規則第28条第1項第4号の休暇を承認するにあたっては、ボランティア活動計画書(別紙様式第2)の提出を求めるものとする。
(休暇簿)
第10条 休暇簿の様式は、別紙様式第3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は次に掲げる記載事項を設ける場合には、別に様式を定めることができる。
(1) 休暇の種類
(2) 期間
(3) 理由(年次休暇の場合を除く。)
附 則
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年4月23日訓令第94号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年5月6日訓令第102号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年6月20日訓令第107号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年6月12日訓令第114号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月27日から適用する。
附 則(平成19年3月28日訓令第144号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月5日訓令第154号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第157号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月27日訓令第162号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日訓令第227号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(週休2日制実施要領及び週休日等の振替実施要領の廃止)
2 週休2日制実施要領(平成9年訓令第85号)及び週休日等の振替実施要領(平成9年訓令第86号)は、廃止する。
附 則(令和4年3月29日訓令第240号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第248号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。